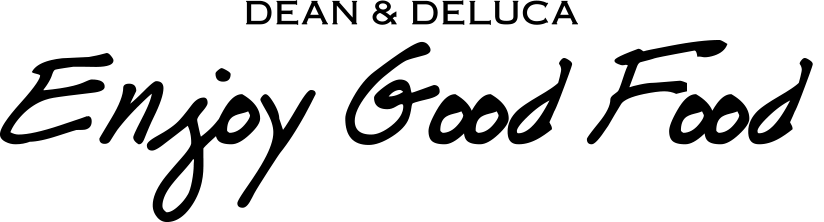
新しいサイトとして
URLが変更になりました
3月21日(木)
サイトがリニューアルオープンしました
3月21日(木)11:00 ブランドサイト、オンラインストアと統合し
3つの公式サイトがひとつになりリニューアルしました。
新しいENJOY GOOD FOODは下記サイトよりおたしみいただけます。
https://www.deandeluca.co.jp/contents/enjoy-good-food/